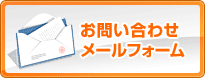ご夫婦で起業した場合、ご主人を取締役(代表)とし、奥様を取締役としない場合や株主をご主人(取締役ではない)として奥様を取締役(代表)とする場合等、様々な組み合わせがありますが、いわゆる同族会社で経営に従事されている方についてお話します。
みなし役員について
皆さん、みなし役員ってご存知ですか?
あまり聞きなれない言葉ですね。
こちら、会社法上の役員にはなく、法人税法上に登場してくる役員です。
すなわち、登記上の役員ではありませんが、法人税法上では役員として取り扱われてしまうということです。
それではみなし役員についてみていきましょう。
みなし役員としての単体名で税法に記載はありませんが、
「法人税法施行令第7条(役員の範囲)及び第71条(使用人兼務役員とされない役員)」を参考にみなし役員を簡略記載しています。
(1)法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)以外の者(社長、専務、常務等)で、その法人の経営に従事しているものをいいます。
例えば、顧問や相談役等、その法人内における地位、職務からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものも含まれます。
(2)同族会社の使用人のうち、次のイ-ハに掲げる全ての要件を満たす者で、その会社の経営に従事しているもの
イ 当該会社の株主グループにつきその所有割合が最も大きいものに順位をつけ、上位1-3位グループの所有割合を算定した場合、次のA-Cのいずれかのグループに属していること。
A 第1順位の株主グループの所有割合が50%を超える場合の株主グループ
B 第1順位及第2順位の株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて50%を超えるときにおけるこれらの株主グループ(合計した結果、50%を超える場合)
C 第1順位から第3順位までの株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて50%を超えるときにおけるこれらの株主グループ(合計した結果、50%を超える場合)
ロ その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること
ハ その使用人(その使用人の配偶者含む)の所有割合が5%を超えていること
以上、条文をまとめてみました。
ここでは経営に従事しているという表現がポイントです。経営に従事するとは販売や仕入、人事他、資金調達など業務を執行する際、意思決定に携わる行為です。
みなし役員に該当した場合
みなし役員に該当すると給与・賞与は全て会社法上の役員と同様になり、定期同額給与や事前確定届出給与の規定が適用されます。
例えば、社長1人で株の所有割合が50%を超える場合で奥様が従業員として働いている場合には前述(2)のイ・ロ・ハ全て満たすこととなります。
奥様を従業員とし、賞与を支給している場合は税務調査で指摘を受けるケースもありますので、注意が必要です。
ただし、夫婦間での相談程度で奥様が経営に従事していない場合はその限りではありません。
奥様に給与を支給している場合等、みなし役員に該当するかどうか、確認されることをお勧め致します。
法人を設立する際、事業資金を少しでも多く確保するため親族や知人から出資を受ける方は比較的多いのではないでしょうか。
その場合、設立後暫くして事業が安定したり逆に厳しくなってくると配当が欲しい、このくらいの金額で買い取ってもらえないかなど出資者からお話があることもあり、法人の代表者さんから税金に関する相談を受けることがあります。
そこで、今回は代表者又は会社が株式(非上場株式)を購入した場合の課税関係について大まかにではございますが書かせて頂きます。
個人(買主)が個人(売主)から購入した場合
1.適正な時価
まずはいくらで売却するかが問題となりますが、基本的にその価値に見合った金額、つまり『適正な時価』で売却を行えば時価-原価の差額、利益に対して税金が課されます。
ただ、この『適正な時価』を巡って考え方の違いや計算方法で裁判になることも多く、ケースにより色々なパターンが考えられるため今回は割愛させて頂きます。
2.適正な時価で購入した場合
①買主
取得時点の課税関係は生じません。
②売主
[売価-原価(譲渡費用等含む)]がプラス(譲渡利益)である場合は譲渡所得税が課税されます。
マイナス(譲渡損失)の場合、同じ年度に他の非上場株式に関する利益が発生していれば損益通算が出来ますが、他の所得とは損益通算出来ず、さらに譲渡損失を翌年度以降に繰り越し出来ません。
3.適正な時価よりも低い金額で購入した場合
①買主
[適正な時価-低い金額]の差額分得をしていることから贈与税が課されますが、その年の贈与を受けた金額が110万円までなら税額は発生しません。
②売主
上記『2.適正な時価で購入した場合』と同じです。
4.適正な時価よりも高い金額で購入した場合
①買主
取得時点の課税関係は生じません。
②売主
[適正な時価-原価]に対して譲渡所得税が課されます。
さらに[高い金額-適正な時価]の差額分得をしていることから贈与税が課税されますが、[3.①]と同様にその年の贈与を受けた金額が110万円までなら税額は発生しません。
法人(買主)が自社株式を個人(売主)から購入した場合
1.適正な時価で購入した場合
①買主
会計上の処理として、購入金額(適正な時価)を取得価額として純資産の部の株主資本のマイナス項目として表示します。(自己株式)
なお、購入金額が購入直前の取得資本金額を超える場合には差額は配当を行ったものとしてみなし配当課税が行われます。
みなし配当に対しては源泉所得税が課税されるため、[適正な時価-源泉所得税]の金額を売主に支払い、購入日の翌月10日までに法人が源泉所得税を納付します。
②売主
上記①のみなし配当部分が配当所得として総合課税の対象となりますが、配当控除の適用を受けることが出来ます。
また、[適正な時価-みなし配当金額]が譲渡所得の総収入金額(売価)となり上記『(1)2②』と同じ取り扱いとなります。
2.適正な時価よりも低い金額で購入した場合
①買主
上記『1.適正な時価で購入した場合』と基本的に同じですが、[適正な時価-低い金額]分得をしていることから、受贈益として課税されます。
さらに、受贈益の分だけ他の株主が得をしたことになるので他の株主に対して贈与税が課税される可能性があります。
なお、取得価額は『適正な時価』の金額となります。
②売主
[低い金額-原価]に対して譲渡所得税が課税されますが、一定の要件(適正な時価×50%未満で売却や買主の法人が同族会社に該当する場合など)は適正な時価で売却されたものとして課税される可能性があります。
3.適正な時価よりも高い金額で購入した場合
①買主
上記『1.適正な時価で購入した場合』と基本的に同じですが、[高い金額-適正な時価]の差額について売主が法人の役員、従業員である場合には賞与として取り扱われます。(役員賞与は損金の額に算入されません)
売主が第三者の場合には寄附金として寄附金課税の対象となります。
なお、取得価額は『適正な時価』の金額となります。
②売主
[高い金額-適正な時価]の差額について、売主が法人の役員、従業員である場合には給与所得、第三者である場合には一時所得として課税されます。
[適正な時価-原価]については上記『(1)2.②』と同じです。
実際の取引を行う場合には上記ケースであっても状況により課税関係が変わってくることも考えられますので、事前に税理士、税務署等に相談された方が宜しいかと思います。
会社設立後の消費税免税のまとめ
前回まで新規に設立した法人の消費税の納税義務についてご紹介しました。
多数の規定がありますのでそのポイントをまとめてみたいと思います。
「新規設立した法人に関する消費税の納税義務のポイント」
ポイント①
資本金又は出資金を1,000万円以上の額で法人を設立すると課税事業者となってしまうため、資本金又は出資金については1,000万円未満の金額で設立する。
ポイント②
1年目の前半6ヶ月の給与及び課税売上高の両方が1,000万円を超える場合は2年目が課税事業者となってしまうため、それぞれ1,000万円を超えないかを事前に試算しておく必要がある。
また、いずれも超える見込みであるときは1年目の事業年度を7ヶ月以下の期間とする。
ポイント③
設立当初から多額の設備投資がある場合や輸出事業を営む場合には消費税の還付を受けられることがあるため、課税事業者の選択を検討する必要がある。
ただし、多額の設備投資をした場合はその事業年度を含め3年間は課税事業者となるためその事業年度だけではなく、3年間の消費税額を合わせて考える必要がある。
ポイント④
新規に設立した法人の資本金が1,000万円以上である場合には、設備投資についての消費税の還付などを意識せずとも、100万円以上の固定資産又は1,000万円以上の棚卸資産の課税仕入を行ったときには、その事業年度を含め3年間は課税事業者となってしまうため購入の前に3年間の消費税を試算する必要がある。
ポイント⑤
3年目以降は基準期間における課税売上高が1,000万円以下であれば原則消費税を納めなくて良いが、1、2年目に行った判定のうち特定期間の判定と1,000万円以上の資産(固定資産と棚卸資産)を購入した場合の特例については1、2年目に限らず引き続き判定を行う必要がある。
以上、ポイントをまとめて説明をさせていただきましたが、取扱いが複雑な規定もありますので、ご不安を感じましたら専門家の方へご相談をいただければと思います。
会社設立後2年目の例外
次に2年目からはどのような場合に課税事業者となるでしょうか?
まずは上記の1年目から適用される規定のうち、「新規設立した法人の資本金による判定」については2年目においても引き続き判定が必要になります。
また2年目においても免税事業者が課税事業者を選択することができます。そして1年目において課税事業者を選択した場合には、その不適用の届出書は翌年は提出できないため2年目も課税事業者となってしまいます。
そしてそれらの規定により課税事業者となった1年目に100万円以上の固定資産や1,000万円以上の棚卸資産を購入して課税仕入を行った場合についても2年目は課税事業者となってしまいます。
更に、上記の規定の他に2年目からは次の「特定期間の判定」が必要になります。
③「特定期間の判定」
前事業年度の開始日から6ヶ月間(特定期間)において課税売上高及び給与(役員報酬を含む)の支払額の両方が1,000万円を超えている場合には、課税事業者となってしまいます。
設立の1年目は前事業年度がないため判定の必要がなく、2年目に判定を行い該当するときには課税事業者となります。
ただし、設立の初年度が7ヶ月以下の期間の場合は特定期間に該当せず翌事業年度も判定が必要ありません。そのため初年度7ヶ月と翌事業年度1年が判定の必要がない最大の期間となります。設立当初から半年で売上と給与の支給額の両方が1,000万円を超えると見込まれるときは、初年度を7ヶ月以下になるように決算月を決定するとよろしいかと思います。
会社設立後の消費税の免税
消費税を納付するかしないかで資金繰りに大きな影響がありますが、そもそも消費税はどの様な場合に納めなくてはならないでしょうか?
法人が国内において資産の譲渡・貸付け、サービスの提供を行った場合には代金を受け取った法人が一般消費者に代わり、消費税の納税義務者に該当することになります。
そのうえで小規模事業者の事務負担を軽減するための事業者免税点制度が設けられており、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者については納税義務が免除されることになります。
基準期間とは、法人においては前々事業年度とされています。新規に設立した法人については1年目2年目に前々事業年度がないため基準期間もありません。そのため原則納税義務が免除されることになります。
そのことから、設立から2年間は消費税を納めなくても良いと言われています。
それでは課税売上高が1,000万円以下の場合や基準期間がなければ必ず納税義務は免除されるのでしょうか?そこにはやはり例外があります。
その例外とはどういったものか、まずは設立1年目から課税事業者となってしまう場合からご説明いたします。
1年目から課税事業者となってしまう場合には「新規設立した法人の資本金による判定」と「課税事業者を選択した場合」に該当した場合があげられます。
①「新規設立した法人の資本金による判定」
基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金または出資金の額が1,000万円以上の法人については課税事業者となってしまいます。そのため設立時に1,000万円以上の資本金にしてしまうと1年目、2年目は課税事業者となってしまいます。
ただし、この規定は基準期間がない場合の判定のため3年目以降は判定が必要ありません。
②「免税事業者が課税事業者を選択した場合」
免税事業者であっても課税事業者選択届出書を提出することにより自ら課税事業者を選択することができます。
高額の資産を購入した場合や輸出事業を営む場合については課税事業者を選択することにより消費税の還付を受けられることがあります。
そのため事業を開始した当初に多額の設備投資を行うときや輸出販売を行うときについては検討が必要です。
①②によって課税事業者となった期間に100万円以上の固定資産や1,000万円以上の棚卸資産を購入して課税仕入を行った場合にはその年を含め3年間は課税事業者となる規定があります。
そのためその事業年度単体の納税額だけではなく、その規定により課税事業者となってしまうその後2年間の納税額も合わせて考慮する必要があります。
この他に合併や分割により新たに設立された法人や、課税売上高が5億円を超える法人やその関係者が株主で設立された新設法人については課税事業者となることがありますので、該当する際には専門家へご相談していただければよろしいかと思います。
会計監査限定監査役の登記
変更登記には経過措置が設けられているので、改正会社法施行後最初に監査役の就任・退任などの変更登記の時に会計監査に限定する登記をします。
(注)改正会社法施行後に定款を変更して、会計監査に限定する旨の定めを設けた会社は2週間以内に登記が必要になりますので注意をして下さい。
1.会計監査限定の監査役とは
非公開会社(株式譲渡制限規定がある会社)は、その監査役の権限を会計監査に限定することができます。(監査役会設置会社と会計監査人設置会社は除きます。)
※監査役の業務には下記の業務監査と会計監査の二つがあります。
○業務監査・・・取締役が会社の職務を法律・定款の決議に従って行
っているか、著しく不当な行為はないかを監査する
ことです。
○会計監査・・・会社の作成する計算書類等が適正に処理されている
かを監査することです。
2.会計監査に限定した監査役とみなされる
旧商法適用の平成18年4月30日以前は、会社の規模により監査役の権限が法定されていました。小会社(資本金が1億円以下で負債総額が200億円未満の会社)の場合、監査役の権限は株式譲渡制限規定の有無に関係なく会計監査に限定されてました。平成18年5月1日以後も経過措置によって、従前の小会社の定款には監査役の権限を会計監査に限定する定めがあるとみなされてました。
上記の会社の様に、定款に監査役の監査権限を会計監査に限定する旨の定めがあるとみなされた小会社であっても後で定款変更により監査役に業務監査権限を付与することは可能です。この場合、従前の監査役は退任することになります。
(注)旧商法の小会社でも、公開会社(株式の譲渡制限規定のない会社)の方は、この経過措置は適用されませんでした。そのため、この会社の監査役は会計監査限定監査役として就任していることから、会社法施行時に従前監査役は退任し、新たに業務監査と会計監査両方の権限を持つ監査役を選任し、その旨登記する必要がありました。
3.監査役の権限を会計に限定すると株主の権限が強化
監査役の権限を会計に限定した会社は、株主が業務監査を行えるように次のように権限が強化されました。
イ.株主は裁判所の許可なく、取締役会議事録の閲覧ができます。
ロ.会社に著しい損害を及ぼす恐れがある時は取締役は、株主に報告
しなければならない。
ハ.株主は取締役が定款違反行為や目的範囲外の行為などに対しては
取締役会の招集を請求することができることになり、取締役会に
出席して意見を述べることもできます。
ニ.株主による取締役の違法行為差止請求権は、「著しい損害が生ず
る恐れ」という要件があれば行使できる。
詳しいことは、司法書士等の専門家の方にご相談ください。